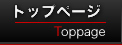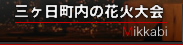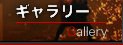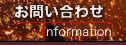手筒保存会の紹介手筒花火のもとは、戦国時代の合戦に通信連絡用に使用された『ノロシ』と思われますが、鉄砲伝来と共に伝わった『黒色火薬』によって一段と進歩し、江戸元禄十三年の頃には『大ノロシ』と称し、当時すでに花火として、煙だけではない鑑賞に耐え得る現在に近い形が出来上がっていたと考えられています。【東三河地方に存在する文献より】三ヶ日町では明治初期には町内の神社神前に奉納されていたと伝え聞いており、 その後現在に至るまで、各地区の夏祭り秋祭りなどで、年を追うごとに数多く奉納披露されています。 七月から八月には、各部落の夏祭りが行われ、十月の秋祭りにも手筒花火・打ち上げ花火が奉納されます。そのような土地柄か、いつとも無く三ヶ日町内の有志が集まり、三ヶ日町手筒保存会を発足致しました。 その後、三ヶ日町役場内、三ヶ日町観光協会の一団体となり、現在は浜松市との合併に伴い三ヶ日町商工会内、三ヶ日町観光協会公認の団体となっています。 三ヶ日町の名を広めるべく、日本国内はもとより、遠く海外(イギリス・カナダ・ロシア・ドイツ)にも遠征に出かけています。 昔は、手筒花火の火の粉をかぶると無病息災といわれ、すぐ近くで奉納しましたが、現在は保安距離の制限があり、火の粉をかぶるようなことはなくなりました。 貴方も三ヶ日町の手筒花火を見て感じてみませんか? イベント出張致します。 手筒花火の種類 (五斤) |
 |